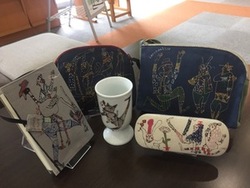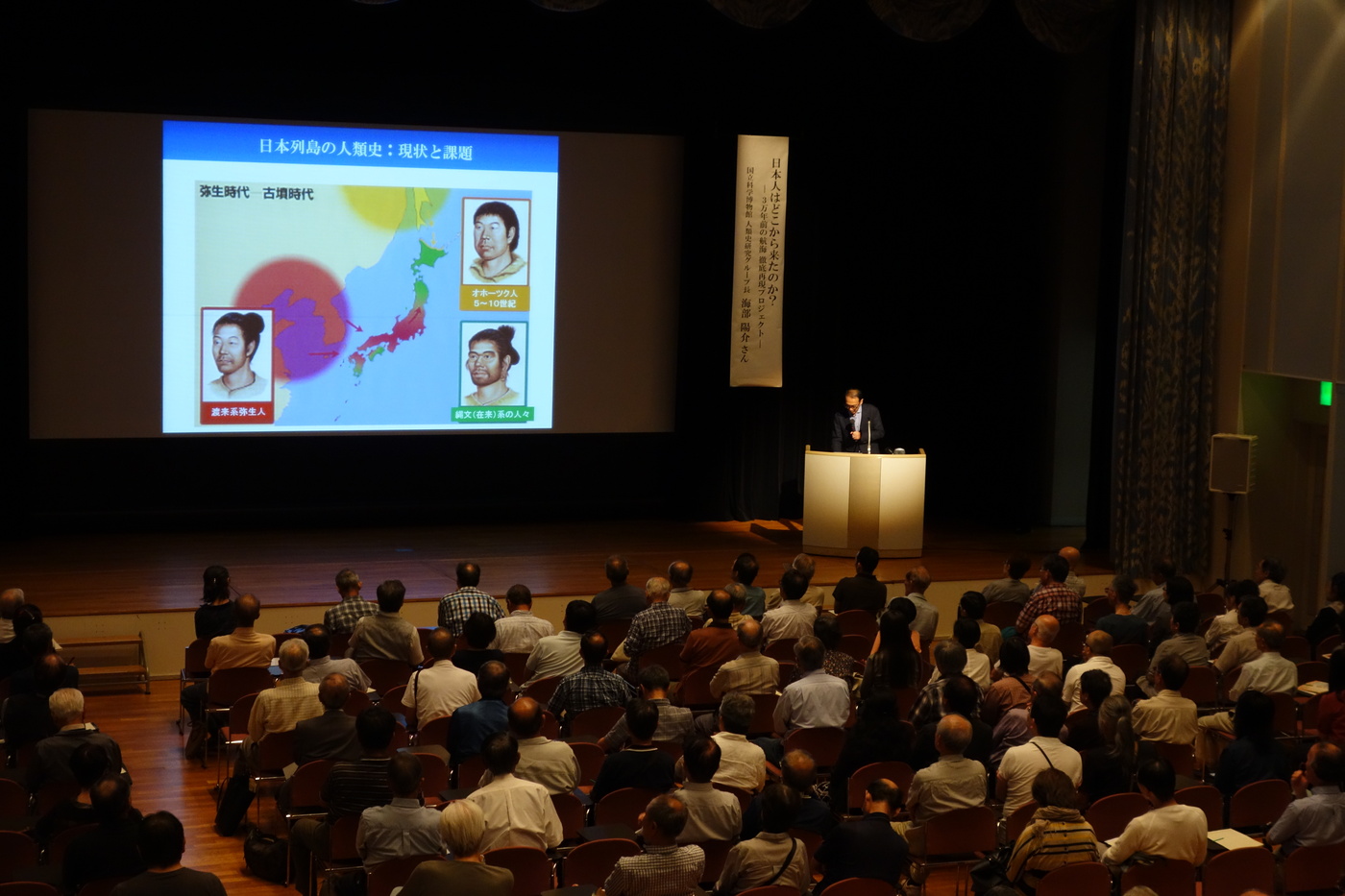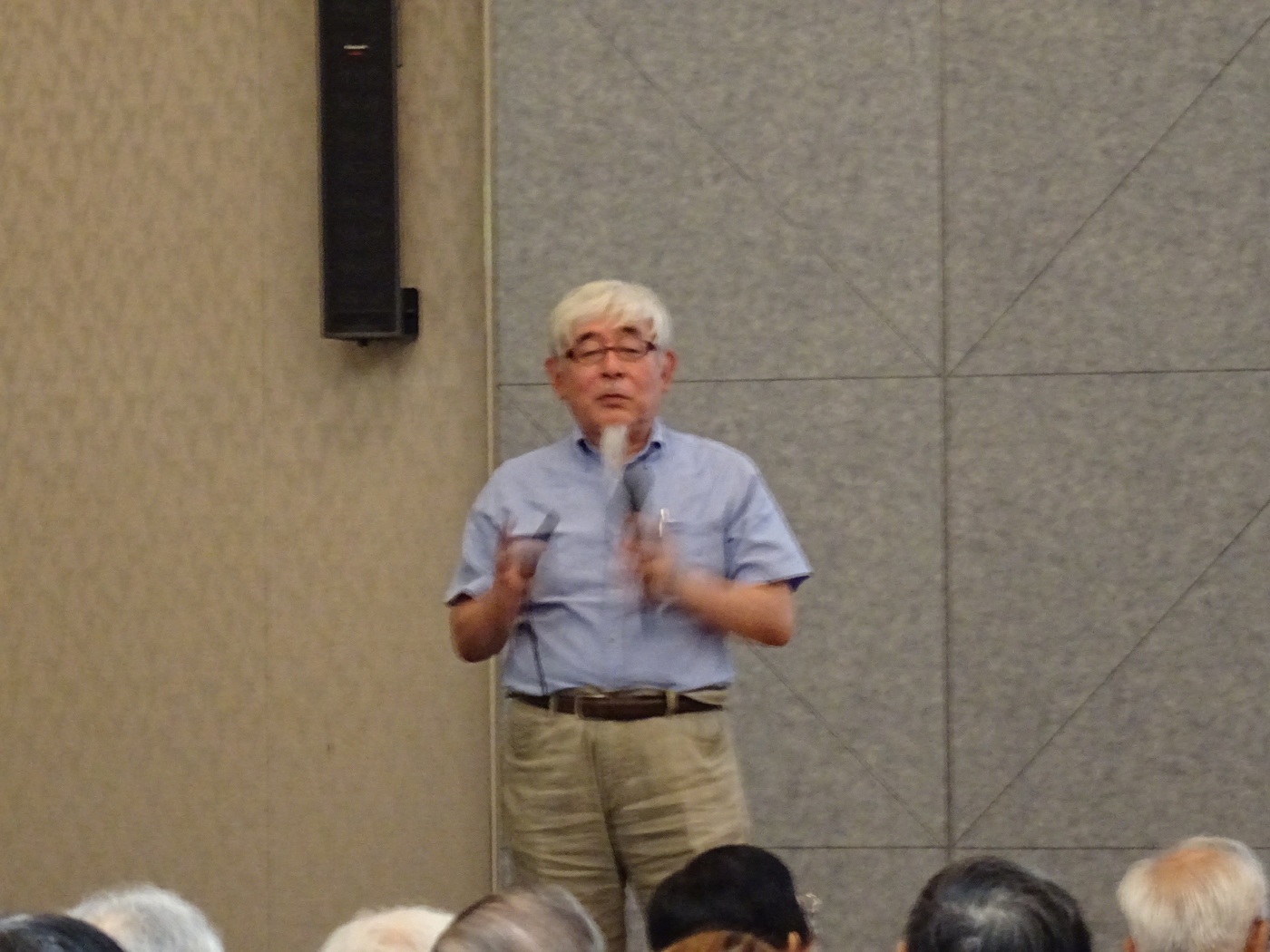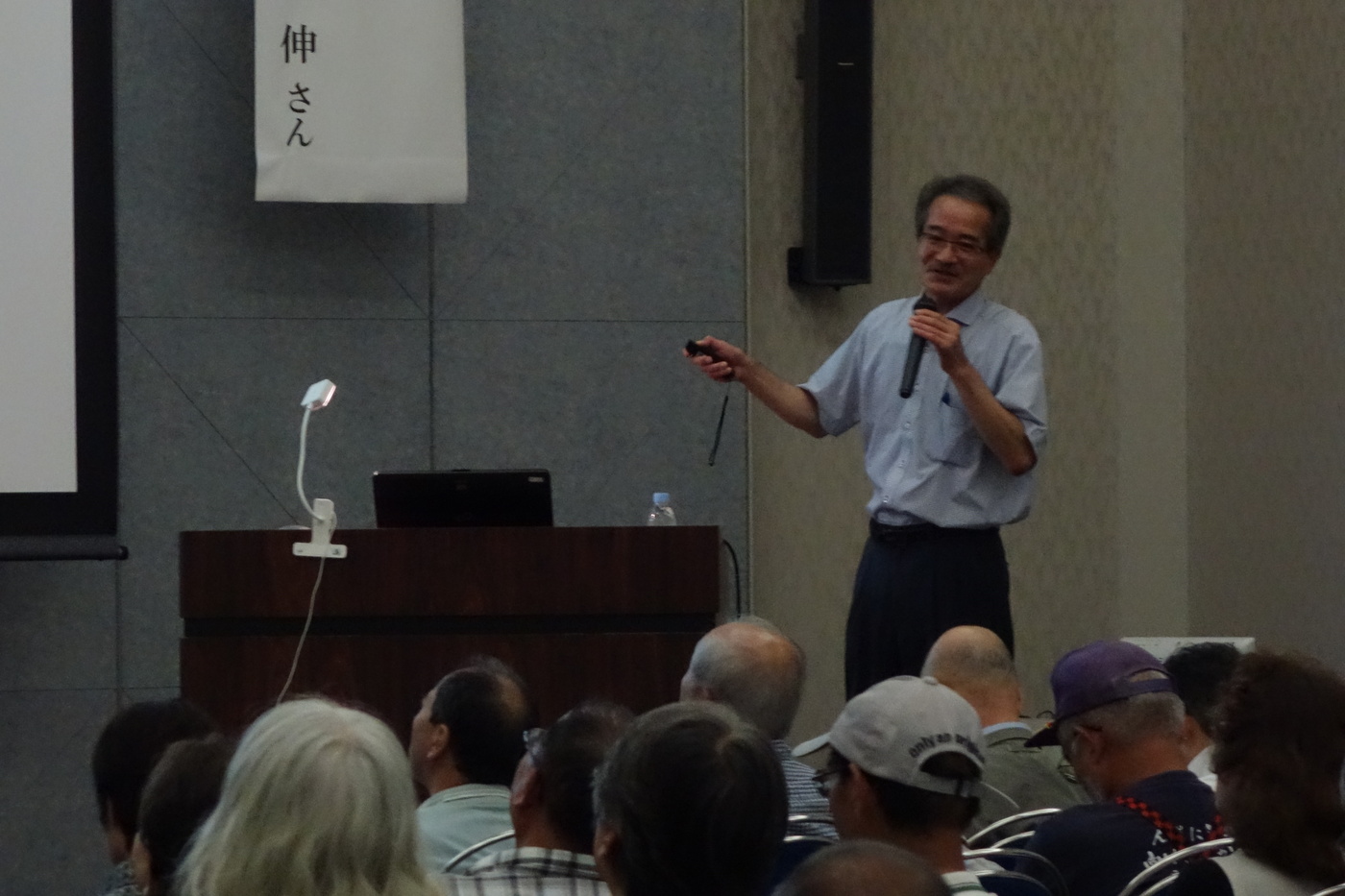「そうぶんの竹あかり」開催しました!
今回初のイベント「そうぶんの竹あかり」は、2017年11月22日(水曜日)から12月3日(日曜日)まで開催しました。
竹あかりのあたたかな光と色づいたもみじがフレンテみえ裏の日本庭園を幻想的な世界に創り上げました。
◆竹あかりの搬入スタート
写真は、竹あかり作家の川渕皓平さん。
慎重に作品の配置を進めていきます。
キャンドルではなくLEDライトが竹の中で点灯する仕組みなので、配線も同時に進めていきます。
川渕さんと職員8名が、常に作業を共にしました。
朝から始まった搬入と設置作業は、日が落ちて外が暗くなってからも続きます。
少しづつ浮かび上がる全体像に、わくわくしながら作業を進めました。
◆来場者数、延べ4,000人を超えた「そうぶんの竹あかり」
11月22日(水曜日)に幕開けした初開催のイベント「そうぶんの竹あかり」。開催期間11日間の来場者数は、延べ4,000人を超えました!!
ゆっくりとカメラと向き合う方、ワンちゃんと一緒にお越しの方、当センターで実施された催しと合わせて観にいらした方、ご家族連れやまたお友達同士と、たくさんの方に足をお運びいただきました。
寒い中お越しいただき、みなさまありがとうございました。

◆竹あかり作家・演出家 川渕皓平さん
作品制作と会場演出を手掛けたのは、竹あかり作家・演出家の川渕皓平さん。
今回のイベントでは、夏に実施した「M祭!2017 キッズ・アート・フェスティバル」内のプログラムで、川渕さんと子どもたちが一緒に制作した竹あかり作品も展示しました。

<アーティストプロフィール>
川渕 皓平
Kohei Kawabuchi
1985年奈良県生まれ。三重県伊賀市在住。
canaarea代表。
2016年三重県内で開催された5月の「伊勢志摩サミット」、9月の「みえレインボーフェスタ」、11月の「海女サミット」で会場を彩った“竹あかり”の制作・演出に関わる。
また、2017年6月1から3日まで、伊勢市で開催した伊勢志摩サミット1周年記念イベント「わわわっしょい!in伊勢志摩」の実行委員長を務め、灯り制作指導・総合演出も手がけた。
2017年8月6日(日曜日)に実施した「M祭!2017 キッズ・アート・フェスティバル」では、子どもたちと一緒に竹あかり作品を制作し、「そうぶんの竹あかり」でも展示した。
また、2017年12月から台湾・台東県内に滞在して芸術交流を行う台東県政府文化処主催の「日台芸術家交流事業」として、書道家 伊藤 潤一と共に、台東県にて芸術交流活動を行う。
◆開催期間中のスペシャルイベントを少しご紹介!
「そうぶんの竹あかり」開催期間中には、スペシャルイベントも実施しました。
◇11月24日(金曜日) 三重県総合文化センターで初開催の「M-PAD」

[M−PADって?!]
「おいしくてあたらしい料理と演劇の楽しみかた」として2011年から晩秋の三重の催事として始まったM-PAD。
三重県内の「おいしい!」お店で自慢の料理を楽しむ。文学・古典作品を俳優の声や身体を通してご覧頂き楽しむ。見終わってから料理や作品を語り合って楽しむ。お店と全国から選りすぐった俳優たちのコラボレーション。素敵なお店で実施しているこの企画。
今年は、初めて三重県総合文化センター内で開催し、カフェ・レストランCotti菜でお食事を、そして竹あかりを舞台に屋外にて上演しました。M-PADのチケットは早々に完売しました。
◇11月25日(土曜日) 新日本フィルハーモニー交響楽団の楽団員による弦楽四重奏のミニコンサート
この日は、大ホールで「久石譲指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団特別演奏会」の開催日でした。コンサート終了後に、新日本フィルハーモニー交響楽団の楽団員による弦楽四重奏のミニコンサートをフレンテ1階の特設会場で実施しました。
1階は立ち見が出るほど満席に、そして2階の通路までお客様が並びました。
フレンテ1階は、素敵な音色に包まれました。
◇11月25日(土曜日) お茶処なごみ 特別営業「夜なごみ」

フレンテみえ1階には、御園棚や野点傘をしつらえました。
竹あかりを窓ガラス越しに眺めながら、お菓子とお抹茶を味わっていただく、特別な夜営業となりました。