取材ボランティアレポート「地球の土ぜんぶ掘ってみた−土と生命の五億年のドラマ−」
テーマから、どのような話になるのか想像できなかったが、土から考える地球・生命・食料についての話であった。
日頃、土については、近くに狭い畑を借りて野菜作りをしており、水はけ、水もちに関心をもつ程度で、あまり掘り下げて考えることはなかった。
この度のセミナーは、学術的な話や専門用語もあったため、少し理解できた事、関心のあった事を自分なりに解釈しその内容を紹介したい。

土とは
土は、岩が分解したものと死んだ植物が混ざったもので、土作りは多様な微生物が関わる超循環型社会で4億年にわたり続いているにもかかわらず、土の研究者は少ないとのこと。そうした中で、進化論の提唱者であるダーウィンは土作りに重要な役割を担うミミズの研究をし、詩人でもあり童話作家として知られる宮沢賢治は、農業の普及員や肥料のセールスをしていたそうです。
地球・生命
地球は46億年前に誕生し、土は5億年前に誕生。その後、保水力のある土に生物(コケ植物等)が誕生し、根の進化、巨大化、キノコ進化、ヒト進化等、時代の経過とともに共進化したそうです。
世界の土、日本の土
ヒトは、水と土が悪いと生きられないため、世界の各地でいい土を求め、その結果として、ヒトが集まり、気候の制約を受けて食文化が形成されたそうです。
『いい土とは、根の気持ちになって考えるといい』とのお話でしたが、風によって砂塵が多く堆積した場所に、いい土壌が多いとの事でした。
日本には主に3種類の土、1.森林の土(褐色森林土)、2.畑の土(黒ボク土)、3.水田の土(沖積未熟土)があり、水田の土の魅力は地質学的な施肥※にあるそうです。
※施肥(せひ):植物に肥料を与えて成長を促し、花や実の付きをよくすること。
土の未来
動植物の死骸をバクテリアが解し形成が繰り返される土壌は、生命の生存基盤である環境を提供するが、人間には土が作れず、劣化するため、メンテナンスが必要であるとのこと。そのための肥料、農法、土を作る挑戦等の説明がありました。その中で、農法は生物性、物理性、化学性により形成が繰り返される土壌と、生産者が得る利益や作物の種類、気候等が関係することから、持続可能な方法はないそうです。
おわりに
今回のセミナーで、土に関心をもつ人、あるいは魅了される人の気持ちが少しわかったような気がした。また、土は人が生きていくために必要な水、エネルギー資源と比べ、人が作れないという点でれ以上に価値のあるものに思えた。
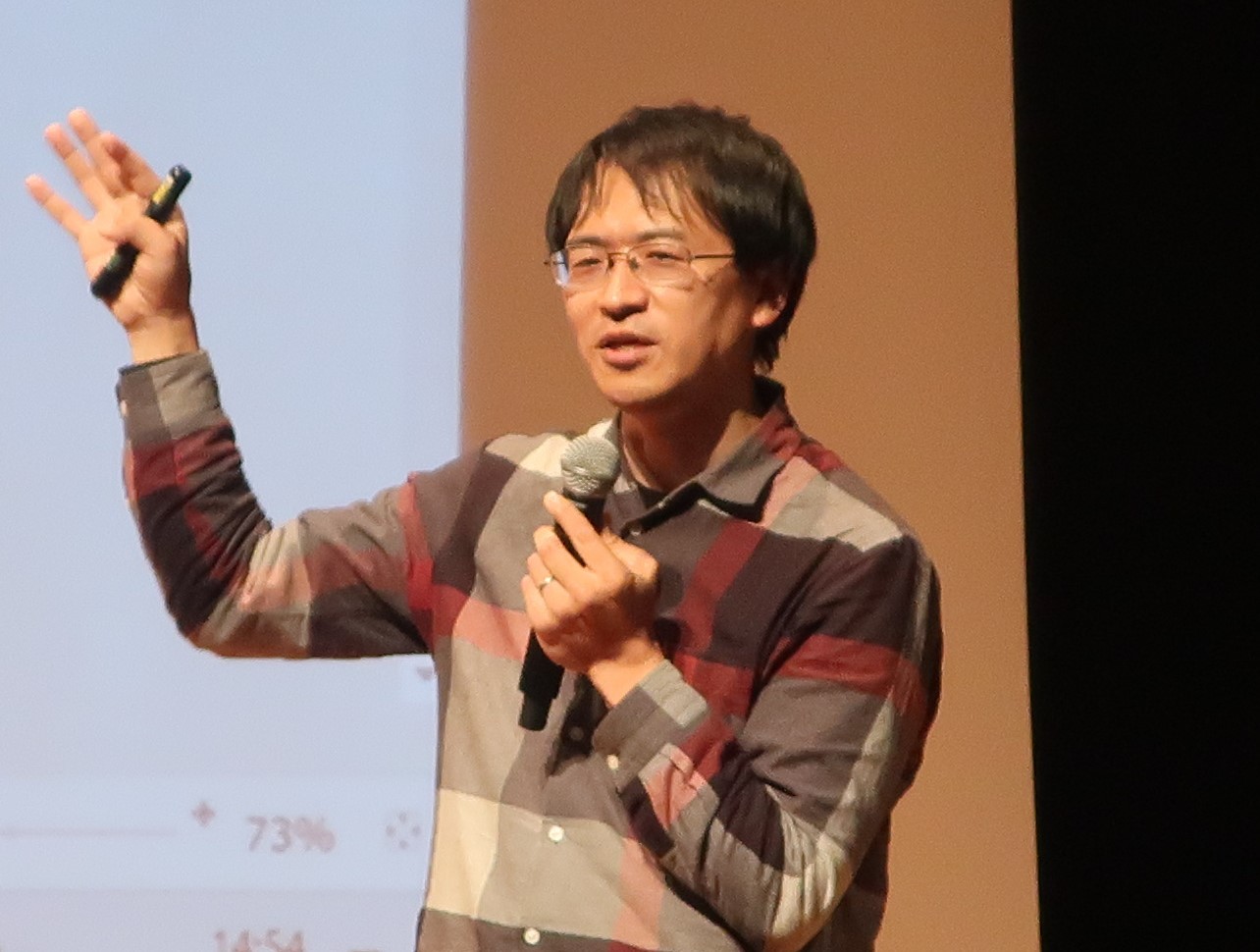

(取材ボランティア:渡邉)
取材したイベント
まなびぃすとセミナー「地球の土ぜんぶ掘ってみた−土と生命の五億年のドラマ−」
2024年12月7日(土曜日)13時30分から
講師:藤井一至 (国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所主任研究員)