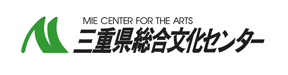ゆうめい10周年の集大成公演「養生」に迫る【完全版】
Mニュース151号にて「ゆうめい」の作・演出・美術池田亮さんのインタビューを掲載しました。紙面には掲載しきれなかった完全版をWEBにてお楽しみください!
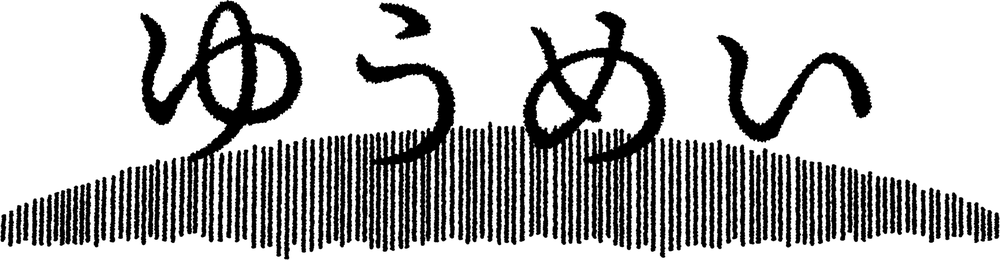
ゆうめい結成のきっかけはミエ・ユース演劇ラボ!10周年の集大成公演「養生」に迫る

演劇をはじめたきっかけ
元々13歳から匿名で小説を書きはじめて、学生の頃から他にも模型とか彫刻づくりや、陸上競技などをしていました。その後墓石職人になりたくて多摩美術大学の彫刻学科に入学して、演劇部に入ったんです。入部がきっかけで演劇と彫刻が近く感じて演劇に興味がわきました。
大学を卒業する頃には演劇を最後にしようと思っていたんですが、ちょうどその頃ハイバイの岩井(秀人)さんが発明したハイバイドアの美術が見たくて。岩井さんと出会って、岩井さんが講師のミエ・ユース演劇ラボ(以下、ミエユース)を紹介してくださったんです。それで2015年に参加して、演劇面白そうだからまだ続けようかなと思いました。
ミエ・ユース演劇ラボに参加したときの思い出
すごく楽しかったですね。大学卒業前の卒業旅行みたいで、その卒業旅行があまりにも楽しすぎたって感じでした(笑)。今まで大学で同世代の人とつくっていたけど、色々な年代の人たちと一緒に何かをつくるっていうのが楽しかったです。各々の体験をもとにつくるのも今まで自分が匿名で書いてた小説やつくってた彫刻に近くて。しかも発表しないと成立しないと思ってたけど、毎日作品が完成してた面白さがあって、日によって全然違う。でも毎回変わる瞬間とか楽しかった。彫刻をつくってるときや匿名で小説書いてるときはずっと一人の世界なんですけど、他者とつくってると自分がこうだと思ってた世界が揺れ動かされる瞬間があって、他の人の存在によってがらっと世界観が変わってひとつに決まらないのが演劇の醍醐味というか楽しみだなあと感じています。
ゆうめい結成
ミエユースが終わって2015年に同じく参加者の丙次とゆうめいを結成しました。結成当初は演劇だけをやろうとは思ってなくて、色々なことをやりたいと思ってました。それで舞台・映像・美術をつくる団体として、ギャラリー公演とか、戯曲より先に美術を考えてそこに物語や戯曲をあてはめてくとかをやり始めてましたね。それもミエユースの影響が強いなと改めて思います。当時自分が舞台監督もやりつつ美術もデザインさせてもらったんですけど、それが他の人が使うことによって自分が想像してたものと全然違うものになったりして。生活の中で家具を別の使い方をするみたいに、自分の考えてる生活とすごく近いようなイメージがありました。
ゆうめいのあゆみ
最初は自分や近しい他者の体験をもとに作品にしていて。2017年に上演した「弟兄」という作品は自身のいじめられた体験を舞台にしたんですけど、自分としてはこんな被害を受けたということを言いたいものではなくて、こういうことがあったから今こういう劇ができたという視点でつくってました。ただ、やっぱり個人的な想いも自分の主観で色濃く偏って見えている時もあるんだなと感じて、それで実体験を演劇化するだけでいいのだろうかという疑問が思い浮かんできて。その後2019年に自分の両親の話を描いた「姿」や、2022年に画家だった祖父と父と自分の三世代を描いた「あかあか」を上演して、自分の父親にも出演してもらって。そこからコロナ禍での舞台芸術の不要不急についても続けていくかどうするかを悩んで。


ゆうめいの公演と同時進行で別のメディア関係の仕事をしている中で、どうしても売れるための教科書は開きっぱなしにしなければならないみたいな、権威的な法則に基づいた応援されやすくて分かりやすいキャラクター像をつくっていくことに比重を置かなければならない瞬間が多くて、ビジネスとしてはとても大事だけど、だれかや自分たちを透明化することに深くつながるとも思っていて。そこで現実や人の複雑な分かりにくさを描く方が演劇だとしたらより広く想像できるのではないかと思ってつくったのが2023年の「ハートランド」でした。評価が一番わかれた作品なんですが岸田國士戯曲賞をいただいて、それまでいわゆる賞レースには興味なかったんですが、賞をとったからには大きな責任があると思って。それで、「ハートランド」のことや、ゆうめいの中で大切にしていたものを失い、もうもどらない瞬間を沢山盛り込んでつくったのが「養生」という作品です。
「養生」について
とっかかりとしては「養生」は全体のストーリーより美術が先なんです。大学で彫刻をやっていたときに腰を壊してしまったのを機に作品を全く作れなくなったときがあって、同時期に夜勤現場によく入っていたんですが、脚立が壊れて廃棄するとき脚立に美術的な要素を感じて。使えなくなったら終わりみたいなことと、腰が壊れた自分がリンクして。タイトルも養生テープと体を休める“養生”とか、“養”って“生”きるなど様々な意味がこめられると思ったのでつけました。

近年の自分やゆうめいも生活の変化によって大事にしたい基準が変わってきて、作品をつくる意味を追求していく中で、今まで大切にしていたクリエイティブの根源部分も結局不確かな権威の基準に則って見失っていたと感じる瞬間が多くて。今の生活をしている自分が描けることはもっと違うものかもしれないっていうのがずっと頭の片隅にあったんです。“芸術と労働と生活”が自分たちに一番密接だったので、それがテーマになる話が必然的にできあがった感じでした。

今までより予算を限りなく削って、育児の合間をぬって少ない人数で、彫刻脳というか空間脳でつくりました。反省点を活かした集大成としてできた実感があったので、お客さんからの評判もすごくよくて、それが読売演劇大賞でも評価されて、今までの自分たちがやってきたことが全面に押し出された作品は「養生」なんじゃないかな、と今になって思います。
初演と全国ツアー版
初演では評判がすごくよくて、「ハートランド」でがらっと作風を変えたけど、少し前のゆうめいに戻って、また少し違うようなちょうどいいところだったなと。
今回の全国ツアー版では脚本も書き直しているので、物語のベースは同じですが、初演で描かれていなかった部分もあるので、初めて観る方も初演を観た方も楽しめると思います。
全国ツアーでそれぞれの劇場に併せて変わる部分
空間として劇場が変わるだけで相当変わると思っています。同じ内容をやったとしても台詞や美術にも変化があらわれてくる。その場所だからできることを探して取り入れていきたいと思ってます。自分が彫刻をやってきたからこその考え方かもしれないですが、置く場所によって同じ形のものでも存在が変わることが養生の描きたいことでもあるので、その土地でしかない楽しさが届けられたらと思います。
三重だと松菱に下見に行ったんですが、時の流れ方が普段の生活と全然違って。自分が昨日こうしていた瞬間にもこの土地にはこういう感覚があったんだろうなと思うと、より視野が広がった感覚がありました。劇場に来るまでも出会えるお客さんはみなさん違うし、流れている空気や天候も全然違うので、感覚的な話ですけどチューニングして毎ステージ場所と合うよう作品にのせられたらと思ってます。
ゆうめいとしても“芸術と労働と生活”を大事にしていきたい
今メンバー全体で育児をしている割合が多いので、自分たちが生活と創作や仕事のバランスを考えている時期です。今後のキャリアと同時に今の時代の変化も感じていて、作品をつくることや仕事に没頭したときに、とりこぼされているものがあるのではないかと考えていて。
育児のために引っ越したんですが、前は気づかなかったことに気づく瞬間があって。取材や、自分が劇場で観劇とか創作して作品のことだけしか考えていないと見落としてたものが多くて、作品のことに没頭し続けるだけでは自分たちにとって良いものはうまれないと感じました。創作以外にも影響を受けてやっていくというのが、自分たちの新しいスタイルの確立にしていきたいと思っています。その方が演劇はさらに楽しくなりそうな気がしていて。例えば自分の世界をつきつめていくと、自分としては匿名で作品をつくり続けてお金をとらない作品をつくるところにいきつきます。今まで舞台・映像・美術をつくる団体として色々なことを同時進行でやってきたんですが、同時にそこに生活も加えていきたいなと改めて思います。
作品としても、ゆうめいとしては元々現実とフィクションとの地続きで演劇をつくっていて、体験も実体験というよりは原体験を基にしているんです。体験したことをテーマにしようとするとそれたことが描きにくくなるんですが、どちらかというとテーマからそれたことを描きたいと思ってますし、それたことこそ大事だとも思っています。軸として考えることはあるけど、それていくのが面白いので、それを物語で描いていきたいですね。
お客さんへのメッセージ
「養生」はゆうめいの自己紹介的な作品でもあるので、ぜひご覧いただいて色々な感想をいだいてほしいです。記念公演は初めてで、まだまだ10年ですが、10年やってきてようやく長く続きそうだと思えるようになりました。変わった部分も変わらない部分もあり、自分たちのカラーがでる凝縮される作品になったと思います。劇中でも10年前と現在を描いているので、作品としてもお客さんにとっても10年を考える機会として、作品だけじゃない体験を含めて劇場を出た後の景色が違うようになるといいなと思います。
ミエユースに参加して三重の劇場でできたことが演劇を続けていくきっかけになったので、演劇の力がすごく強い場所だなと思っています。そういう意味では凱旋公演というか、感謝や報告をする場所に、帰って来たという感じです。三重によってこんな団体が生まれて、こんな作品ができたというのを届ける作品にして、楽しんでもらいたいです。
あとは大きな空間で3人芝居とか、美術も脚立と養生テープっていうシンプルな美術でもこういうことができるっていうことが色々な人の発見になるとは思ってて。演劇はお金や時間をかけないといけない部分もありますが、お金や時間をかけなくてもできるものに触れられたらなあと思ってます。同じく演劇やものづくりをしている人たちとも影響し合えればいいなと思っています。
ハイバイドア:ハイバイの岩井秀人さんが発明した、ドアノブが宙に浮いているような舞台装置
ミエ・ユース演劇ラボ:三重県文化会館が2014年~2018年(上演年)に実施していた、高校生から25歳以下の若手を対象に期間限定疑似劇団をつくる企画

「養生」あらすじ
美大生の橋本(本橋 龍)と、大学生の阿部(丙次)はショッピングモールや百貨店の内装を行う夜勤バイトで出会った。正社員のことをネタに「卒業したら絶対ああならない」と陰で笑い合う。数年後、二人はその夜勤の正社員になっていた。
阿部は家庭を持ち、辞めそうな新入社員の清水(黒澤多生)を教育する。作家を目指していた橋本は、著名作家となった同期が百貨店の人気ギャラリーで個展を開くことを知り、その広告設営を担う。
夕方から明け方の夜勤劇。

作・演出・美術 池田亮
1992年、埼玉県生まれ。13歳から原体験をもとにした小説を匿名でネット上に発表し続けた経験を機に、ルポルタージュやメディア脚本等の様々な媒体で執筆を担う。墓石や玩具など、人の心が生み出す物体にも傾倒し、立体造形や空間について学ぶ。東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。2015年「ゆうめい」を結成。全作品の脚本・演出、多くの美術を手掛ける。2024年『ハートランド』で第68回岸田國士戯曲賞を受賞。2025年『養生』で第32回読売演劇大賞優秀演出家賞を受賞。造形作家としても活動し、原案・カプセルトイの原型を手がけた『クリスタルハンドルの水栓リング』が全国流通。
公演情報
ゆうめい10周年全国ツアー公演「養生」
11月8日(土曜日)14時開演
11月9日(日曜日)13時開演
会場:三重県文化会館 小ホール
チケット:整理番号付自由席/
一般3,500円 U-39 2,800円 U-25 2,000円 U-18 1,000円 障がい者割引 2,500円(同伴の介助者1名無料)
チケット発売:9月27日(土曜日)
問合せ:三重県文化会館チケットカウンター 059-233-1122
Mニュースvol.151(2025年9月発行)