三重のまなび2011・まなびぃすとセミナー「最後の斎王・祥子とその父・後醍醐」
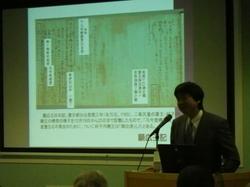
斎宮歴史博物館で開催されている特別展「後醍醐 〜最後の斎王とその父〜」に関連した講座が開催されました。
飛鳥時代に始まった斎王制度というのは、天皇家の権力や財力を目で見えるかたちで象徴する存在であった。しかし、中世には武家勢力が台頭し、朝廷の権力が弱体化するにつれ、斎王制度も衰退化していった。そういった状況は世相にも現れ、鎌倉時代の文学の「とはずがたり」などでは、かつてのような神聖化した斎王は見られなくなってきているということも説明されました。
その後、後醍醐天皇の建武政権が成立すると、その象徴のひとつとして斎王制度を重視し、そのときに祥子内親王が選ばれ斎王になったが、伊勢の地に赴くことなく建武政権崩壊とともに斎王制度も終焉を迎えてしまったというお話をされました。
今回の特別展では、“後醍醐天皇画像”や、かつては足利尊氏像とされていた“騎馬武者像”、後醍醐天皇の手印のついた“四天王寺縁起”など貴重な資料が数多く展示され、大変見ごたえのあるものになっていると説明されました。
後半では、斎宮のボランティア「かわせみ座」さんによる、「ながこひめの斎王えにっき」紙芝居も上映されました。
生涯学習センター1階のエントランスでは、斎宮歴史博物館のミニ展示が9月23日から11月13日まで開催されており、熱心に展示を見ていかれる方も多くいらっしゃいました。
☆講座開催情報
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
時間 13:30〜15:30
共催 斎宮歴史博物館
講師 斎宮歴史博物館
筒井 正明 さん
参加人数 131名
参加費 無料
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
☆参加者の声
・南北朝時代を駈け足での講演でありましたが、ゆっくり現物を見ながら勉強したいと思います。ありがとうございました。
・これまで中世の歴史の話を勉強したことは、学校時代以降で初めて聞き、時代の状況がよくわかった。
・紙芝居とても良かったです!!


