令和3年度人材育成講座(伊賀市・1回目)「絵本の世界の楽しみ方 -紙芝居との比較を通して-」の事業報告
令和3年度の伊賀市人材育成講座は、ユマニテク短期大学 幼児保育学科長・教授 川勝泰介さんを講師にお招きし、児童文化・保育の視点から、絵本や読み聞かせについてお話ししていただきました。

講座では最初に絵本の歴史が紹介されました。 絵本は絵と言葉を使用した「表現メディア」でもあり、構成に特徴のある絵本や、翻訳に工夫がある絵本、ページのめくり方に工夫が凝らされた絵本、文字で表現された絵本など様々に工夫された絵本があることを実物を手に取りながら説明されました。
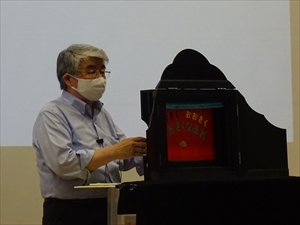
絵本の楽しさはページをめくる楽しさにあると講師は語ります。
ページをめくることで、新しい世界を発見することができ、その子どもにとって未知の世界と出会います。「五感」での直接体験や絵本を介して、子どもたちの想像力は働き、そしてその想像力は思考力へとつながっていくのです。
大人は読み聞かせによって、子どもたちへ絵本の楽しさを伝え、想像力を育てることができます。
読み手に取って、絵本の世界を伝えるためのテクニックももちろん大切ですが、一番大切なことは読み手自身も絵本を楽しみ、子どもたちと楽しい時間を共有する姿勢であると締めくくり、本日の講座を終了しました。
-
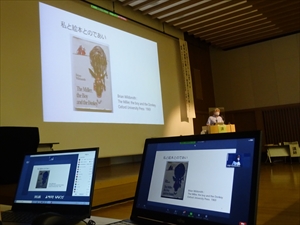
オンラインでも講座を配信。他市町からもたくさんの参加をいただきました。 -

講座で紹介された絵本が展示され、みなさん、興味深く見学していました。 -
事前に募集した質問にも丁寧に答えていただきました。
受講者の方から事前いただいた質問に答えていただきました。
質問1:絵本の中で、何人かの登場人物がいる場合、声を変えた方が良いのでしょうか?(例えば、女の人なら女の人らしい声で、男の人なら男の人らしい声で、子どもなら子どもらしい声で)
回答1:一般には、登場人物の違いがわかる程度に自然に読むのがいいとされています。登場人物によって極端に声色を変えると、絵本より読み手の「話芸」を楽しむことになります。あくまでも主役は絵本であることを忘れないでください。
質問2:動物でも同じでしょうか?強そうな動物なら怖そうな声で、可愛い動物ならそれらしい声を出すべきでしょうか?
回答2:これも質問1と同じですが、強そうな声・怖そうな声も人によって異なります。そして、かわいい声とはどんな声でしょうか。自然と出てくる声で読めばいいと思います。声優や俳優のまねをする必要はありません。
声色を気にするより、オノマトペの表現やリズムカルな読み方を工夫した方がよいと思います。
質問3:絵本を読んでいく中で、アドリブ等を入れても良いのでしょうか?
回答3:作者は絵本制作の段階で、練りに練って作り上げていきます。
読み手はそれを尊重すべきだと考えます。アドリブはその場で即興的に入れるものです。安易にアドリブなどを入れては、絵本の世界が台無しになってしまいます。同じように、読み聞かせの途中で質問を挟むというのも、物語を中断してしまいますので、避けましょう。
絵本によっては子どもたちに問いかけてみることが有効な場合もありますが、基本的に、物語絵本は、最後まで読み通し、楽しむことが大切です。お勉強している時のように質問がたびたび入ることはやめておきましょう。
また一般的に、読み終えたあとに、「おもしろかった?」「どこがおもしろかった」などと感想を求めることも避けた方がよいとされています。
子どもたちの表情や発語を見聞きしていれば、おもしろかったかどうかはわかるはずですし、読み聞かせしながら子どもたちの反応をみることも大切です。
質問4:コロナ禍においてソーシャルディスタンスを実施しているなか、赤ちゃん(0歳から3歳)の読み聞かせでの選書が難しくなっています。大型絵本、紙芝居などで対応していますが、なかなかお話の数が少ないため、毎回同じお話でマンネリ化しているように思います。打開策を教えて頂けませんでしょうか?
回答4:まず赤ちゃんを0歳~3歳としているのは疑問ですし、年齢の低い子どもたちはできるだけ少人数での読み聞かせをしてください。
また2歳から3歳になるとずいぶん好みもはっきりしてきますので、その年齢の子どもたちがどのような作品が好きそうかを考えて、選書してください。
最近は赤ちゃん絵本も多種多様です。数の限られた大型絵本や紙芝居にたよるのではなく、いろいろな絵本を探してみてください。
質問5:図書館で「赤ちゃんタイム」の時間、現在はコロナで行っていませんが、市の育児相談の時間に、おおむね0歳~3歳ぐらいの親子に対してボランティアをさせていただいています。
現在、大型絵本や大型紙芝居がたくさん整備されています。1対1での読み聞かせの時は使いませんが、育児相談の時など、複数人でばらばらと座って見えるとき、大型の絵本の方が見やすいかなあと使わせていただいたりしましたが、低年齢の子どもさんにとって、大型絵本は、視野の中に全部入るのでしょうか?そのことを考えると、いいのかなあと迷ったりしています。
回答5:視野に入るかどうかはわかりませんが、赤ちゃんには赤ちゃんにふさわしい絵本があります。大型絵本は、赤ちゃんに向いたものがあるとは思いませんので、できるだけ年齢にふさわしい題材の絵本を選ぶか、絵本にこだわらず、人形などを使っておはなしするのも一つの方法かと思います。
質問6:乳児さんは、絵本のおしゃぶりが多いです。家での本のおしゃぶりは推奨しますが、図書館ではどうでしょうか。コロナ禍では、とてもできませんが、平常時でもどうかなと思いながら、親さんには「本をしゃぶることも大事よ、何でも口に入れて確認していくのだから。」と言って、むやみやたらと止めたりはしなかったのですが、図書館のようなところでは、どうしたらいいのでしょうか。
回答6:乳児はものをなめることを通して、外界の事物を認識することは確かですが、それで絵本をしゃぶらせることがいいのかは疑問です。それでは、絵本がおしゃぶりの代わりになってしまいますし、大切な絵本がぐちゃぐちゃになってしまいます。
また使われているインクのことも心配です。乳児の場合は、周りの大人が手に持って一緒に読むようにするといいのではないでしょうか。
- 絵本ボランティアをやっていましたが、知らない絵本をたくさん知ることができ、よい刺激になりました。もっと絵本のチェックをしないとと改めて認識しました。最近、紙芝居に目ざめています。抜き・さすに注意して活用したいと思います。
- 自分の子供達は成人しましたが、図書館での読み聞かせの時に、ハラハラドキドキワクワク、を感じられる時間を地域の子供達と共に共有し、楽しめることを、改めて有り難く嬉しく思いました。あまり読む機会のなかった紙芝居も、「抜き」の強弱を意識して演じ手となってみようと思います。ありがとうございました。
- 日頃、読み聞かせの機会があり、これまでの経験から当たり前に思っていたこと、また忘れていたことが、今回の講座で、改めて、方法や技法についてその意義などを論述的に学び直させていただくことができました。ありがとうございました。
- 読み聞かせボランティアをしています。こんなやり方でいいのだろうかと思うことが度々あります。今日のお話を聞いて、選書の仕方・注意・心得は再確認できたこともあり、来月からの読み聞かせに生かせそうです。

