もっと楽しく!パパの子育て
映画『ダブルシフト―パパの子育て奮闘記』
スウェーデンより来日!マリア・エッセーン監督舞台挨拶&映画上映
スウェーデンは、社会福祉の先進国・男女共同参画の先進国と言われています。女性も男性も仕事を持ち、男性の育児休業取得率は80%近く、子育てにも夫婦ともに関わりを持っている国です。
フレンテみえでは、4月28日(金)、29日(土・祝)の2日間、「もっと楽しく!パパの子育て」をテーマに、スウェーデンから監督をお招きし、監督舞台挨拶&映画「ダブルシフト - パパの子育て奮闘記」上映、監督講演&シンポジウムを開催しました。また、三重県子育て情報交流センターとの共催で交流会や、フレンテみえオリジナルパネル展「スウェーデン式 仕事と子育ての両立」も開催しました。
監督の講演やシンポジウムの様子を抜粋して紹介します。
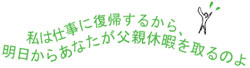

タクシードライバーのヨーナスとお天気キャスターのエマに子どもが生まれた。8ヶ月間仕事を休んで子育てをしていた妻エマは、「明日からあなたが育児をしてね」とヨーナスに宣言して仕事に戻ってしまった。しかし、小さな会社で働くヨーナスは、育児休暇を言い出すことができない。ダブルシフトな毎日がヨーナスを追い詰めていく・・・!
北欧の男女共同参画の先進国 スウェーデンに学ぶ
男女ともに仕事と家庭の両立を目指す国
エッセーンさん 作品を上映した日本、インド、アメリカでは、上映後、子育てにおける父親の役割について議論が起きました。監督としては、このフィルムがいろいろな国で違う捉え方、リアクションにあうというのは嬉しいことです。
スウェーデンでは一定の出生率を保ちながら、女性が労働参加をしているのですが、主に2つの理由があります。 ひとつは手厚い両親保険(育児休業中の給与保障)ということ、もうひとつは児童擁護といった学童保育などがあることで、女性たちはこういった制度に支えられています。
出生率というのは、子どもを持つということと、働くということが両立している国により高くなるという傾向があるようです。ですから、政府は子どもがいる家庭への支援というのを非常に手厚くしているわけです。
スウェーデンの家族政策は、とりわけ1960年くらいからの広範な社会変化によってつくられたものです。
そのうちの重要な変化のひとつとして、労働力として、男女が家から出て働き始めた人が増えて、男女共同参画という動きにつながり、今日、男女も家事育児について、前よりも一層責任分担ということをするようになっています。
スウェーデンの最終的な家族政策の最終目標は、男女ともに仕事と子育てを両立できるということです。家族政策によって、より平等な社会づくりが促進されなければならないということなのです。
マリア・エッセーンさん

ストックホルム大学で映画を学ぶ。
テレビの仕事を経て1993年コロムビア大学に入学のため渡米。在籍中に製作した短編2作品は数多くの国際映画祭で上映され賞賛を受ける。卒業後、映画以外にもNYとストックホルムでコマーシャルなども手掛け、長編デビューとなったこの作品にもキャリアを生かしている。1968年、スウェーデン生まれ
社会全体で次の世代を担う
伊田さん 僕は大学の教員なんかもしていますが、結婚もしていないし、子どももいないです。子どもは好きだけど、産まなかったというか作らなかったわけで、これから持つ、というのは養子も含めてあるかもしれませんが、僕は持たない人生もありだと思います。もし、持つなら育児休業も含めて子育てをしないとあかんと。
僕は、社会全体で次の世代を担ったらよいという考えなんです。たくさん税金を払って、みんなで子育てや介護をしていく。そういう意味では独身であったり、子どもがいない人も関わったらいいと思うし、逆に産んだ人もキャリアを我慢せずにしたいことをやっていくと、そんな社会になったらいいなと思って、ジェンダー論、男女平等論をやってるんです。そういう意味では、北欧から学ぶことはいっぱいあると思います。
伊田 広行 さん

立命館大学非常勤講師。日本女性学会幹事。執筆・講演活動、さまざまな市民運動なども行う。
男女平等・人権問題・社会政策・労働問題・家族/恋愛問題、平和問題、人生(生き方)論をジェンダーとシングル単位の視点から考察している。近年は、〈スピリチュアリティ〉を組み込んだ人権論/人生論の確立やスピリチュアルケア論の研究、自殺防止センターでの電話相談ボランティアなどに取り組んでいる。
育児休業を取ってみたら家事もついていた!
山本さん 私は2ヶ月間、育児休業を取りました。取ってみてどうだったかということですが、子どものご飯作って、オシメを替えて…こんな毎日が続くわけです。いざ休みを取ってみて改めて気づいたのは、育児休業は育児だけじゃないということなんです。
で、何があったかというと家事があったんですね。当たり前のことだと笑われるかもしれませんが、これがかなり負担に感じました。その日しないとあかんことを自分なりに考えて洗濯したり掃除したり、天気のいい日は布団も干さなあかん、あるいは雨が降りそうやから洗濯物は早く取りこまなあかんとか、そういうのが全然意識から抜けていて、育児休業というのは家事もしないとあかんのやなということでした。
この子の命を、たった2ヶ月だったけれど自分に任され、なんとか無事乗り越えた。そういう安心感みたいなものが正直ありますね。
山本 智佳央 さん

三重県職員。現在は三重県児童相談センター北勢児童相談所に勤務。
県庁健康福祉部に勤務していた平成14年4月から2ヶ月間、育児休業を取得。この時、「育児休業の楽しさ」と同時に「家事との両立の大変さ」・「育児の孤独さ」も身を持って体験する。 2度目の育児休業にチャレンジするかどうか悩んでいる最中。(H18年4月1日現在)
山本さん 子育て中は、被害者意識が強くなるというか、自分ばかりが子育てや家のことをしているという感じになるんです。私が休みを取って子育てに専念しているわけですが、実は妻のほうが仕事から帰ってきて、子どもの面倒をたくさん見ています。もちろん、家事もです。しかし、なぜか私ばかりがさせられているような感覚になるんですね。それで、ついつい「俺にばっかり言うな」などと言ってしまったりするわけです。なるほど、世の中のお母さん方はこんな心持になるんやなとすごく感じて、お母さんを責めるのはよくないな、かえってマイナスやなということが本当に実感できました。
男性の子育て参加がないと成り立たない選択肢
坂倉さん 映画を観て、子育ての大変さを思い出しました。子どもが病気になった時、夫は「自分は休めない」と言うし、私も休めない。でも「母親がみるのが当然だろ」と言われて、いつも私が休んでいたなというのを思い出しました。私が子育てをした頃から40年近く経ち、育児休業制度も整ったのですが、まだまだ特に男性にとっては取りにくい。
私はどっちかというと育児休業なんて取らないで働き続けたいと思う方で、男女ともに働き続けられるような条件整備をしてほしいと思っています。スウェーデンの育休の取り方は100通りもあると聞いたことがあります。100通りもあるならば、そのひとつの選択をするというのもありかなと思いました。
坂倉 加代子 さん

NPO法人「四日市こどものまち」理事、NPO法人「四日市男女共同参画研究所」代表
愛知県立女子大学卒業後、四日市市役所へ。青少年課課長、女性課課長、教育次長などを歴任。2000年退職。三重大学客員教授も務めた。
ワーク・ライフ・バランスの実現には
社会のシステムの変革が必須
坂倉さん 一人ひとりの「ワーク・ライフ・バランス」を実現しようと思うと、これは社会的なことだなと思います。バランスをとるために、例えば労働時間を短くしなければいけない。男女の賃金格差や税制も問題になる。スウェーデンは税金を個人単位で掛けたことで、「ワーク・ライフ・バランス」が進んだということですね。保育園や学童保育所の整備なども必要ですし、「ワーク・ライフ・バランス」は、構造的な社会のシステム変革がなければ実現しないテーマだと思いますし、男女共同参画社会には必須条件だと思います。
スウェーデンのように自立した個人としてバランスをとる
伊田さん 今日のテーマの「ワーク・ライフ・バランス」というのは仕事と生活のバランスのことです。具体的には、仕事以外の時間として、自分のための時間、親しい人、家族、友達との時間とか社会地域をよくするための時間とか、自分個人を単位とするということなんです。
北欧と日本と何が違うか。日本の家族の場合は、家のことも仕事をするのも2人でひとつ。どちらかが仕事ばっかり家事ばっかり、ということになってしまいがちで、これだと個人のバランスはあまりよくない。北欧は個人として自分で決めるというかなり自立した自己決定意識が強く、そういう中では仕事もしたい、子どもも持ちたいという「ワーク・ライフ・バランス」のバランスが個人単位であるわけです。
講演後のインタビューから・・・
日本は先進的だが考え方は親世代と同じ

来日は2度目です。日本は進んだ国という印象が強かったんですが、滞在するにつれちょっと違うなと思い始めました。しきたりとか慣習などということが固持されている。古さと先進的な部分の2面性があると思います。そこが日本の面白いところでもあると思いますけどね。
30歳代の若い男性が「日本の女性は男性より子育てが向いている」と言うのを聞きました。若い人がそんなことを言っているのが心配ですね。それは、ちょうど私たちの親世代の頃に言われていたことです。スウェーデンでは、教育が功をなしてか、若い世代は両親世代の考え方とは違ってきています。
スウェーデンも取組真っ只中
男女共同参画社会推進のために、スウェーデンは30年にもわたって様々な取組をしてきました。その結果、女性議員割合は高く、育児休業制度など、仕事と子育てを両立するためのシステムは充実してきています。
しかし、まだ50:50ではないですし、民間の大企業の役員クラスの女性が占める割合は低いのが現状です。
1974年頃のフェミニズムを扱った演劇と同じものが今でも上演されていますが、内容は現代社会でも決して古くない。男女共同参画の歩みはそれほどスローなのです。
映画の世界でも、女性監督がまだ少ないという現状があります。その状況を変革しようと、女性監督作品を40%にまで増やそうとする動きがあるなど、いろいろな方面での取組が進められようとしています。
日本も時間はかかるかもしれませんが、努力を積み重ねていくことが大切なのではないでしょうか。
スウェーデンの育児休業制度
1974年、スウェーデンでは世界初の両性が取得できる育児休業が導入されました。これは、経済危機に直面した税制改革の成果であるともいえます。かつて、スウェーデンも専業主婦が多い国でしたが、働く女性が増えたのは、この育児休業制度が整ったことも大きな要因のひとつです。子どもを産むことが決まったら休みが保障され、賃金も80%もらえます(両親保険)。社会全体で子どもにかかる費用を支えるしくみができているといえます。
スウェーデンの育児休業取得率
女性 民間 84.0%、公的89.3%
男性 民間 79.2%、公的75.7%
(出典:内閣府経済社会総合研究所「スウェーデン企業におけるワーク・ライフバランス調査」)
また、育児休業取得日数が480日と長いのも特徴です。
- 夫婦で育児休暇を取るとよいと思いました。
- 父親の育児参加はやはり企業や社会の問題が大きいと思います。
- フレンテみえでのこのような取組を続けてほしいです。
- 仕事と子育てで大変さばかりが先に立っていたけど、今自分がしていることの楽しさ、大切さを感じました。

