男性講座専門コース
表現してみよう! 伝えたいメッセージ
~フリーペーパー、ポスター、絵本などを作ってみよう~
メディアを読み解く力を学びながら、実際にミニ新聞、ポスターなどを作成しました。
男女がいきいきと輝ける社会づくりのために、男女共同参画の視点を持って地域で活躍する男性の人材育成のための講座です。
メディアの女性表現・男性表現って?
第1回、2回は、講師の諸橋さんのメディア・リテラシーについての講義とグループワークを行いました。
メディアは意図的に構成されたもので、「女性」「男性」のイメージを現実に作っているものであるというお話があり、TVのCMや報道番組を通して、実際にどのように番組が構成され、どのような印象を与えているのかということを知るグループワークを行いました。
視聴者側も男女共同参画の視点を持ってメディアに接し、様々な観点で読み解く力をつけることが必要であるとのことでした。
また、グループワークでは、報道番組やテレビコマーシャルを見ながら、必要以上に、男女の固定的役割分担などのある一定の価値観や固定観念が繰り返し報道され、植えつけられていることや、それらの番組が無意識に流れていることなどに気付きました。
第2回の公共広報物を切り抜くワークでは、女性の写真が内容とは無関係なのにイメージのために使用されていたり、食の分野では女性だけが多く登場していることから、公共広報物においてもまだまだ男女共同参画の視点が薄いということなどという課題も出されました。
いよいよ作成!~今度は発信する側として~
第3回では、三重テレビ放送報道制作部の小川秀幸さんに実際の現場ではどのように番組が作られているのかといったお話をいただき、作成物のコンセプトについて話し合いを行いました。いよいよ作成!
講義では「番組作りには何を伝えたいのかという強い思いがないとだめ、コンセプトをしっかり持つことが大切」といったお話があり、発信者側の立場でメディアを捉えました。
グループワークでは、2つのグループに分かれ、「家庭における固定的役割分担意識の解消」をコンセプトに「ミニ新聞」と「ポスター」を作成することを決定しました。
第4回には、中日新聞三重総局記者の奥田哲平さんより、作成のための編集や取材などのスキルについてお話いただきました。見出しの付け方や効果的な紙面構成についての講義に加え、様々な立場の読者を意識した言葉選びなどへの配慮についてもお話がありました。また、作成物の具体的な内容について話し合いが行われ、メイン記事や取材、読み物といった構成から、どのようにすればわかりやすく伝わるかといったアイデアを出し合いました。
第5回は、小川秀幸さんを再び講師に迎え、作成物を男女共同参画の視点で見直しました。「伝えたいこと」が伝わっているかなどについて、参加者で意見交換を行いました。
完成までには、講座のほかにも取材などの活動を行い、何度も自主ミーティングを重ねました。
男女共同参画フォーラムでの発表
第6回は、「男女共同参画フォーラム~みえの男女(ひと)2007~」のワークショップで作成物の発表を行いました。
男性グループ主催の「ちょいワルカフェ」でコーヒーを飲んでいただきながら、受講生自らミニ新聞やポスターの説明をしました。多くの女性・男性がカフェを訪れ、参加者からは、「このような男性がいることは大変心強いこと」「父や夫にこの新聞やポスターをみせたい」といった感想もあり、大変好評をいただきました。
男女共同参画社会を推進する一員として
最終回となる第7回は、振り返りとまとめを行いました。再び諸橋泰樹さんにお越しいただき、新聞やポスターの講評や男女共同参画の視点についての復習を行いました。講座を終え、受講生から「これからも講座を受講した仲間としてフレンテみえを中心につながっていきましょう」と呼びかけがあり、「フレンテMen’s club」が発足。今後につながる動きもできました。
男女共同参画を進める一員として、修了生たち男性の活躍がますます期待されるところです。
諸橋 泰樹 さん
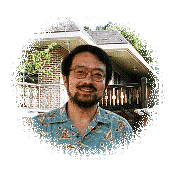
大学院在学中から(社)日本新聞協会研究所で委嘱研究員として各種メディアの調査研究に従事ののち、1993年から尚美学園短期大学教員。1999年よりフェリス女学院大学教員。地方自治体の男女平等条例づくりや男女平等計画づくりなどに携わる機会が多く、現在、小金井市男女平等推進審議会会長、和光市男女平等審議会会長、渋谷区男女共同参画アドバイザーほかを務めている。
<著書>「雑誌文化の女性学」「ジェンダーの罠」「ジェンダーの語られ方、メディアのつくられ方」「ジェンダーとジャーナリズムのはざまで」「ジェンダーというメガネ」「季節の変わり目」
