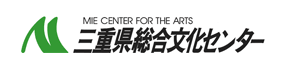インタビュー記事
「“離れていてもアートでつながる”老いの暮らし」
三重県総合文化センター情報誌Mニュースvol.143(2023年9月)
「老いのプレーパーク」が、コロナ禍でどのように工夫しながら活動を続けていったのか?自粛生活中の日記やオンラインでの活動を振り返りながら、メンバーたちの座談会の様子をお届けします。
https://www.center-mie.or.jp/mnews_web_edition/files/m143web.pdf
「えんげきで超高齢社会を豊かに」
三重県総合文化センター情報誌Mニュースvol.126(2019年6月)
2018年12月、三重県文化会館小ホールで初舞台を踏んだ「老いのプレーパーク」のメンバーたち。本番にいたるまでの活動の様子や、客席の反応などをご紹介します。
https://www.center-mie.or.jp/mnews_web_edition/files/m126.pdf
「演劇×(ニカケル)老い」
三重県総合文化センター情報誌Mニュースvol.119(2017年9月)
2017年からはじまった”介護を楽しむ””明るく老いる”アートプロジェクト。プロジェクトのパートナーである菅原直樹さん(俳優/介護福祉士)に、演劇と老いの相性の良さについてお話をうかがいました。
https://www.center-mie.or.jp/main/files/Mnews/119-web.pdf